
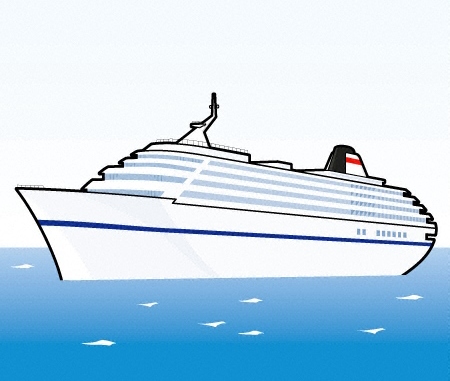

|
| 26 インタビュー会場の会議室に入ると、スタッフが準備を整えて待っていた。 正面に、メインキャスターの中里がいた。そして、岸本の座る車椅子がその横に位置し、福山が続いた。 その向かいに佐伯と若木が座り、横に音声担当の森田がいる。テーブルには付いていないが、出入口のあたりに、事務長や警備員も腰掛けている。 「では、定刻になりましたので、始めさせていただきます。私は、今回の企画を提案しました関東プロデュースの福山と言います。よろしくお願いします。もう、オーシャンドリーム号の沈没から20年という歳月が過ぎましたが、その原因も良くわからないまま今に至っています。改めて、その時の犠牲者のご冥福をお祈りしたいと思います。そして、唯一の生存者である、ここにいらっしゃいます岸本耶須子さんにお会いする機会が出来まして、本当に嬉しく思っています。また、今回のインタビューに応じていただいた岸本さんをはじめ、こちらの事務長さんや、この企画にご協力いただいたみなさんに心よりお礼を申し上げます。ということで、私からの挨拶はこれくらいにして、まずは、それぞれ簡単な自己紹介をして、今日の進行を岸本さんにもご説明したいと思います」 スタッフやそこにいる人たちの自己紹介が終わると、番組の進行の段取りが佐伯から説明され、簡単なリハーサルもした。 その間、福山は、岸本の姿を見ていた。丸顔で、目のぱっちりした人形を思わせるような綺麗な顔立ちをしていた。長い間の療養生活で大変だろうが、思っていたより元気そうに見えた。そして、時折見せる笑顔からは、どことなく、少女のようなあどけなさも感じられた。 「では、よろしいでしょうか。音声さんもいいですか」 「はい、OKです」 「途中、何か言い間違えたと思っても、とりあえずは気にしないで続けてください。では、本番行きます。はい、スタート」 佐伯の掛け声で、番組の収録が始まった。 中里のリードで、今回のインタビューの趣旨や岸本や福山の紹介があった。そして、中里の方から近況について岸本に聞いていた。 「では、今回のインタビューの企画をされました福山さんにバトンタッチして、引き続き岸本さんにお話をお聞きしていただきます。福山さん、よろしくお願いします」 「分かりました。では、改めまして福山と申します。岸本さん、今回は、本当にありがとうございました。今、ご紹介いただきましたように、あの事故当時、私は、T新聞の記者で、毎日、その取材をしていました」 岸本は、緊張気味に福山の話を聞いていた。 「その時に疑問だったことは、今に至るもまだ解決していません。今日、岸本さんにお話が聞けることになり、それらの疑問が少しでも解決できたらと願っているところです。では、あの事故から20年になりますが、まず、このインタビューのお話があってどう思われましたか?」 「私は、唯一の生存者で、あの時に父も母も妹も失いました。先ほどもお話しましたが、それ以来、祖父母をはじめ、多くの人たちに本当にお世話になりながら、どうにかやって来れています」 岸本は、それまでのことを振り返りながら話していた。 「それ以後、特に、何かを聞かれることもありませんでしたし、私の方から、あまり、話す気にもなれませんでした。でも、それでいいのだろうかと思うこともありました。今回、このお話をいただいて、とうとうその時が来たのだなと思いました。私の知っていることをお話しすることで、少しでも何かのお役に立てるのなら、ご協力させていただこうと思い、お受けすることにしました」 「そうでしたか、ありがとうございます。では、早速ですが、あの船に乗っておられて、まず、どんな異変がありましたか?」 「確か、ドーンというような、あまり大きな音ではありませんが、聞こえたように思います」 「それは、どの辺りからなのか分かりますか?」 「どうでしたでしょうか。遠くから聞こえたといった感じでしたから、どこから何の音なのかといったことは分かりません」 「では、それについての船内放送とか説明はありましたか?」 「その音がした後に、何かエンジンのトラブルがあったので、しばらく停船しますという放送がありました。でも、救命胴衣を付けろとか、避難しろといった放送は無かったように思います」 岸本の話を、周りの者も、静かに聞き入っていた。 福山が、ふと見ると、警備員も真剣に聞き入っているようだった。警備員までがインタビュー会場に入っていることに少々違和感を感じたが、病院の警備員としては、患者の安全を確保することが最大の任務なのであろう。決して、目を離してはいけないといった姿勢が感じられた。しかし、そうは言っても、眼光が厳しすぎるのではとも思った。まあ、仕事柄そうなるのかもしれない。 黒岩もメモを取りながら聞いている。 そして、話は、次第に核心に迫っていった。 「その放送のあった時は、どうしていましたか?」 「部屋に居ました」 「では、その後は、どうしましたか?」 「特に危険な状況にあるとも思いませんでしたし、妹と夕食までの時間、デッキに出て海を眺めたり、バレーボールで遊んだりしていました。周りの人たちも普通に過ごしておられたように思います。そうだ、確か、私がボールを受けそこねて転がったボールを拾いにデッキの端の方に行った時だったでしょうか。突然、激しい光や音と共に、吹き飛ばされました」 「光ったのですね」 「そうですね。オレンジ色のような強い光が後ろから光ったように思います」 「後ろというのは、あなたの後ろなのか、船尾なのかどちらでしょうか」 「船尾の方だったように思います」 「それからどうなりましたか?」 「何が起こったのかは全く分かりませんでした。気づいたら海の上に浮かんでいました。目の前には、船の一部のような物が浮かんでいて、それに紐で括られていました。おそらく、誰かが助けてくれたんだと思います。でも、その周囲には誰もいませんでした。真っ暗でしたし、ただ浮かんでいるだけでどうしようもありませんでした」 福山は、聞いているだけで、背筋が冷たくなるような恐ろしさを感じた。 「何か、聞こえたり、見えたりしませんでしたか」 「遠くでヘリコプターの音がしていました。ライトで海を照らしているようでしたが、声を出して届くような距離でもありませんでしたし、声を出す力もありませんでした」 「他に何かを見ませんでしたか?」 「私、今でもそれが現実なのか夢なのかよく分からなくて、一度、おばあちゃんに話したことがあるんですけど、おばあちゃんは、きっと夢を見ていたんだよって云うだけで、私もそうなのかなあって、それ以後は誰にも話していないんです」 「それは、どういった夢ですか?」 「本当に怖い夢なんです。でも夢なんでしょうね、きっと・・・」 そこまで話すと、岸本は、話が途切れた。 「どんな怖い夢でしたか?」 「余りにも変な事だから、やめておきます」 「そうですか、それ以外には何か気づいたようなことはありませんでしたか?」 「その後、次第に明るくなってきて、ヘリコプターの音もしなくなりました。もう、私は、見捨てられたんだと思い悲しくなりましたが、そのうち、船がやってきて助けていただきました。その時は、本当に嬉しかったです。でも、私以外に誰も助からなかったと聞いてまた悲しくなりました。私が分かるのは、それくらいでしょうか」 佐伯から、エンディングへ向かう合図がでた。 「では、時間も来たようですので、最後に、今一番の願いは何ですか?」 「今ですか。そうですねえ。本を出したいですね」 「本ですか?」 「はい。そんなことが出来るかどうか分かりませんが、今までのことや、今思っていることなど、いろんな夢を綴ったようなエッセイ集でしょうか。せめて、そんな生きた証が残せたらなあなんて思っています」 「なるほど。私はいろいろ出版社も編集者も知っていますから、いくらでもお力になりますよ。友人にも作家がいますし、もし、出版されるというならいろいろアドバイスもできますよ」 「本当ですか、ぜひお願いします」 「分かりました。では、その夢が実現できるように頑張りましょう。今日は、本当にありがとうございました」 「こちらこそありがとうございました。何か、一歩前に進むことが出来たように思います。これからもどうか力になってください」 「分かりました。お任せください」 そこで、中里がまとめに入った。 「岸本さんに力強い味方が出来て良かったですね。今日は、オーシャンドリーム号の唯一の生存者である岸本耶須子さんにお話をお聞きしました。今日のインタビューが何らかの進展につながればと思います。岸本さん、今日は本当にありがとうございました。岸本さんが、これからも元気で頑張っていただけるようにと願っています。本日、インタビューを担当したのは、関東プロデュースの福山勇一さんと、私、中里喜美惠でした」 「はい、OK」 無事、収録が終わった。 「お疲れ様」 「お疲れ」 スタッフが機材を片付けだした。 福山は、岸本に近寄り声をかけた。 「岸本さん、本当にありがとうございました。お陰様でいい番組になりそうです」 「あんな話で良かったんでしょうか」 「いえいえ、貴重なお話でした。それに、エッセイ集を出したいというのも、前向きで、とても素晴らしい夢だと思いましたよ」 「そんな、お恥ずかしいです。でも、これから、少しずつ書き留めていこうと思います。ある程度できたら、本当に出版社を紹介していただけますか?」 「もちろんですよ。いくらでもご相談に乗ります」 「ありがとうございます」 付き添いの看護師が車椅子を動かそうとしていた。 福山が、窓からふと外を見ると、先程の警備員が警官に何やら話しかけていた。そして、警官は何か納得した様子で、他の二人の警官にも声を掛けていた。 どうも、任務完了ということのようで、警官は帰っていった。あとは、警備員にお任せくださいとでも言ったのかもしれない。手際の良い警備員だ。 「中々核心に迫るインタビューだったな」 管理棟を出た所で黒岩が声をかけてきた。 「そうだな。おそらく核兵器が使用されたことに間違いはなさそうだ。それによって短時間で撃沈された。その後の証拠隠滅やマスコミ対策も抜かりがない。こんなことは、あらかじめ周到な準備がなければできないことだ」 「そうだろうな」 「そして、彼女は夢かもしれないと言っていたが、意識が朦朧とした中で何かを見たのだろう」 「何をだろうか」 「怖い夢だと言っていたよ。彼女が口にするのもはばかるほどの、おばあちゃんに話しても、きっと夢を見たんだよと言われてしまうような、そんな夢だ」 「まさか、彼女は、・・・」 「そうだなあ。あるいは、そのまさかかもしれない。後始末という、まさに地獄のような光景をな」 ちょうど、二人が話しているその横を、岸本が車椅子で病棟へ移動していった。 軽く会釈を交わして、二人は車椅子を見送った。 二人は、岸本が、まだとてつもない記憶を心の奥底に秘めているように思えた。 「そうなると、彼女は、まだまだ安全だとはとても言えないぞ」 「そうだよなあ」 不安に感じながら岸本の乗る車椅子を背後から見ていたが、その不安はすぐに現実となった。その横には進木が言われた通りに付いていたが、その後ろから警備員の一人が近づいていた。警備をしているにしては、福山には、どこか変な動きに思えた。ふと見ると、その警備員の手には光るものが握られていた。 「ええっ!」 いったい、どういうことだ。なぜ警備員が、そんな行動を取っているのだろう。福山には咄嗟によく分からなかったが、とにかく岸本に危険が迫っていることだけは確かだ。だが、福山が駆け出してももう間に合いそうもなかった。 福山は叫んだ。 「危ないっ! 雪絵ちゃん、その警備員がナイフを持っているぞ」 進木が振り返ると、ナイフを手にした警備員が、恐ろしい形相で迫っていた。 『えっ、何なの?』 自分に向かってきているのか、あるいは岸本なのかよく分からなかったが、どちらにしてもこの警備員が危害を加えようとしているのは分かった。 進木は、何か対抗できるものがないか周囲を見回した。すると、その横のベンチに、老人が二人腰掛けていた。そして、その一人は杖を持っていた。 進木は、すぐにそのお年寄りの側に行き、その杖を手にした。 「ごめんなさい。ちょっとお借りします」 その杖を手にすると、進木の目付きが変わった。鋭い、剣士の目になっていた。 そして、警備員が看護師を振りはらい、岸本にナイフを振りかざしているその手を目掛けて杖を振り下ろした。 「小手~」 進木の甲高い声が響いた。 その警備員の手からナイフが落ち、警備員は自らの手首を押さえた。福山は、防具もなしに、あの技を食ったら、まず骨折は免れないだろうと思った。 さらに、進木は、再び、杖を高くかざして、『面』を入れようとしていた。 インターハイで3位の進木の「面」をまともに食らったら、命をも心配しなくてはいけない。福山が、ストップの声をかけようとしたら、もう一人の警備員が駆けつけて、警棒でその杖が降り下ろされるのを止めていた。 そして、その警備員を怒鳴りつけた。 「お前は、何をやっているんだ。こっちへこい」 腕を庇いながら歩くその警備員を連れて行きながら、何やら耳打ちしていた。 すると、その岸本を襲った警備員が突然逃げ出した。 「ちょっと待て!」 もう一人の警備員が叫んだ。 そして、進木がその後を追い、福山の横に居た黒岩も駆け出した。 騒ぎを聞きつけて管理棟から出てきていた事務長も彼らの後を追った。 福山も追いかけようとしたが、もう一人の警備員が追わずにいることに、疑問を持った。あるいは、みんなの注意をもう一人の警備員に引きつけようとしたのなら、この警備員も怪しい。 福山は、追うのを止めた。すると、岸本の車椅子は、病棟の玄関の近くにいたが、すでに警備員はその側まで近づいて、懐からナイフを取り出していた。 「やめろ、やめるんだ!」 もう間に合いそうにない。 その警備員は、岸本の横に居る看護師を威嚇している。 「危ない!」 福山の横に、佐伯や他のスタッフも駆けつけてきた。 「そうだ。ちょっと、ごめん」 福山は、佐伯のポケットに入っているボールを取り出した。そして、そのボールを左手に持ち、投球フォームに入った。腰の辺りにボールを構え、大きく前に足を踏み出すと、福山の左腕が、地面すれすれのところから前へしなる様に弧を描いた。ボールは、福山の手を離れ、『シュッ』という音を立て、一直線に警備員めがけて飛んでいくと、パシッという音と共に警備員の持っていたナイフが飛んだ。 元甲子園出場投手の球がまともに腕を直撃したらたまらない。その警備員は、腕を押さえた。そして、先ほどの警備員とは逆の方向に逃げ出した。 福山が駆け出し、スタッフも後を追った。福山は、しばらく追いかけたが、見失った。だが、身元はすぐに分かるだろうと、深追いするのはやめた。 病院へ戻ると、もう一人の警備員を追ったメンバーも戻ってきた。やはり、逃げられたようだ。 「事務長さん、すぐに警備員の身元を教えてください」 「と、言われましても、私どもの方では誰なのかは分かりません」 「えっ、こちらの病院の警備員では?」 「いえ、違います。私は、放送局の方でご準備されたのかと思っておりました」 「こちらでは、そのようなことはしていません。・・・、一体、どういうことだ?」 そこに、黒岩もやってきた。 「やっぱり、罠だったようだな。しかし、あいつらは何者なんだ」 「病院側が知らないとすると、残るは、この取材を知っているあのどちらかということか。まあ、行ってみるしかないようだ。さあ、黒岩、行くぞ」 「行くって、どこへ」 「まずは、横浜だ」 「横浜?」 二人は、黒岩の車へと急いだ。 |


邪馬台国発見
ブログ「邪馬台国は出雲に存在していた」
国産ローヤルゼリー≪山陰ローヤルゼリーセンター≫
Copyright (C) 2011 みんなで古代史を考える会 All Rights Reserved.