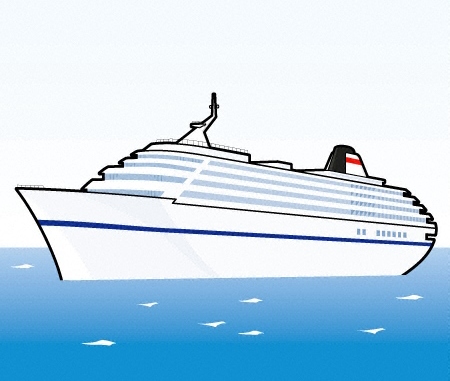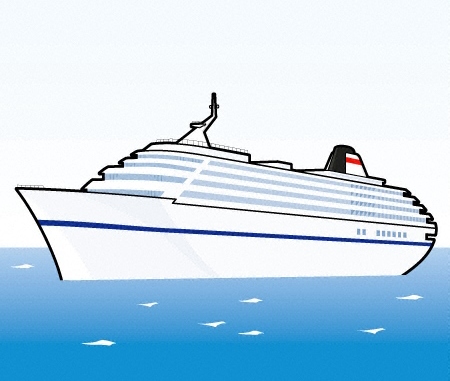|
5.
福山が予約していた「葵」という小料理屋に行くと、奥まった部屋へ案内された。そこだと、少々込み入った話も気兼ねなくできる。
「やあ、待たせたかな」
「俺も、ほんのさっき来たところだ」
黒岩は、ネクタイ姿で、まだ現役の記者といった風貌があった。
「先ほどの横浜FMを聞いていたよ。かなり、思い切った話をしたようだな」
「そうか。相当オブラートに包んだつもりだったんだがな。まあ、今までとは、ちょっと違う切り口だったことに間違いはないだろう。本当は、もっと赤裸々に語りたいんだが、公共の電波ではそうもいかんよ」
「記者をしていた頃から比べると、随分丸くなったな。あの頃のお前は、そんなことを気にするような奴じゃなかった。許せないことに対しては一歩も後ろに引こうとはしなかったし、これが正しいと思い込んだら一途に突き進んだ」
「そうだったかなあ。そんな純粋な記者じゃないよ。ただの馬鹿だっただけだ」
二人は、やってきたビールで乾杯し、前に置かれた付き出しをつついた。
「ところが、今は、そんな馬鹿な記者が居なくなっちまったよ」
「えっ?」
「ああ、失礼。つまり、上司やスポンサーに気を使い、世渡り上手な賢い連中ばかりだってことだよ。そう言う俺もその中の一人なんだろうけどな。今、防衛庁関係を担当しているんだが、殆ど、記者クラブで発表される情報を記事にするだけで、戦時中の大本営発表と変りゃしないよ。あの頃、お前と、走り回っていた頃が懐かしいよ」
「そうか。だが、そんな愚痴をこぼすために来た訳じゃないんだろう」
「ああ、この前、A大佐の証言の話をしただろう。つまり、俺が、対策本部で耳にした情報は、本当だったということになる。そうなると、では、どうしてそのまま救助に向かわせなかったのかだ。それは、自衛隊が救助に向かっているから、必要ないということだった。これが、A大佐の証言だ。仮にだよ、自衛隊が、その事故を把握していたとしたら、大型客船だから、できるだけ早く多くの船が救助に向かうようにしようと考えるはずだ」
「そうだ。救助を最優先に考えた場合、それが当然だ。しかし、米軍の救助を断っている」
福山は、相槌を打ちながら、次第に黒岩の話に熱がこもってくるのを感じた。
「では、どうしてそういう判断をしたかとなるといくつかのパターンが考えられる。その第1は、小規模の事故で米軍が出動するまでもないという場合。しかし、今回はあの通り大惨事になったから、その判断ではない。次は、もうすでに救助の大半を済ませたから必要ないという場合。それも、当てはまらない。そうなると、あとは、非常に卑劣な判断だというところに行き着かざるを得ない」
「どういう判断だ」
「その事故の状況を把握した自衛隊は、すでに行ってもむだだと知っていたか、あるいは、何らかの理由で、そこへ行かせたくなかったのかもしれん。大型客船が瞬時に沈没するなど通常はあり得ない。救助の時間があると判断するのが当然だ。どちらにしても、緊急避難した生存者がいると考えるだろう。そうなると、米軍に救助されると何か都合が悪いと判断したということにならざるを得ないんだ。では、何がどう都合が悪かったのかということになってくる。つまり、そこには、秘匿しなければならない何かがあったということだ」
「それは、何だ」
黒岩は、ビールを一口飲むと、大きく息を吸って静かにはいた。
そして、福山の目を見つめながら言った。
「オーシャン・ドリーム号沈没の原因と何らかの関係があったからだよ」
「自衛隊がか?」
「自衛隊か、あるいは米軍か、あるいは双方ともか」
「どういうことだ」
「俺は、今、防衛庁の担当記者だから、いろいろ調べることができる。だから、先週、お前に話してからも調べている。すると、あることが分かった」
「どんなことだ」
福山は、黒岩が何を言い出すのか息を呑んだ。
「あの付近の海域は、米軍の訓練海域だということだよ」
「ああ、それはA大佐も言っていたよな」
「そこに、当時の状況を加味して考えると、ある想定が浮かんでくる」
「想定?」
「その当時、アメリカは、巡航ミサイル『トマホーク』の開発に力を入れていたんだよ。そして、日本もそれに協力しており、その試行訓練が行われていたようだ。つまり、魚雷の実験だよ」
「魚雷だと?」
「魚雷型巡航ミサイルだ。スクリューやエンジンなどを追尾していくから、いくら相手が逃げようとも必ず追いかけて破壊するという悪魔のような魚雷だ」
福山は、黒岩の驚愕する話からその先を想像すると、恐ろしさのあまり背筋が冷たくなるのを感じた。
「その魚雷でやられたというのか?」
「さあ、それはどうかまだ分からない。しかし、その実験は、対空型巡航ミサイルでも行なわれているんだよ。無線で操縦できる無人の仮想敵機を飛ばし、それを撃ち落とさせるといったことも行われていたそうだ。そんなことは、一般には公開されていないがな。その仮想敵機は、分かりやすいようにオレンジ色に塗ってあるんだ」
「オレンジ色ねえ」
「そこで、当時のドリーム号の調査資料を調べてみたんだよ。つまり、そういった実験が行なわれていたとしたら、仮想敵船、つまり、おとりに使われていた船が必ずあったはずなんだ。そういった残骸が残されてなかったかどうかということだ。すなわち、その実験に何らかの形で巻き込まれてしまった可能性があるんだよ。オーシャン・ドリーム号は、定期便ではないから、米軍あるいは自衛隊もその通過を認識できていたか分からない。ドリーム号もまさかそんなところで、そういった実験が行われているなどとは思わない。そういったことにより、たまたま接触するといったハプニングが生じたのではないかと俺は思っている」
「で、その残骸はあったのか」
「はたしてそうかどうかよくは分からないが、オレンジ色の線が入った板のようなものが写っていたんだ。おそらく、あれは、そのおとりに使っていた船の一部のようにも見える」
「今、その残骸は見れないのか?」
「何とか、俺も調べようとしたのだが、防衛庁の管理になっていて、とても手が出せそうにないよ」
「なるほど、都合の悪いものは見せないということか。ということは、自らに隠そうとする何らかの動機があるとも言える。しかし、今の話は、かなり真相に近づいてもいるようだが、まだ憶測の域を出ていない。もう少し、確証となるものがないとどうにもならないよ」
「そうだ。そこで、お前の力を借りたいと思って今日は来た」
「俺の?」
「そうだ」
「どういったことだ」
黒岩は、背筋を伸ばした。
「真相究明には、必要なことが3つある。まず第一には、調査資料のさらなる検証だ。それは、俺でも何とかなる。もう一つは、米軍や自衛隊の関係者からの情報だ。米軍は簡単にはいかないから、自衛隊員からの情報収集だ。そして、あの事故での唯一の生存者との接触」
「生存者との接触だと?」
福山は、思わず身を乗り出した。
「ああ、お前も知っているだろうが、あの時、『岸本耶須子』という少女が助けられているが、その後の消息は、ほとんど知られていない」
「その少女に当時の様子を聞くと言うのか」
「そうだ。自衛隊員と生存者への取材だ」
「確かに、核心に迫ることになるだろうが。その可能性はあるのか?」
「つてが無いこともない。ただ、新聞記者というだけでは、ちょっと難しい。T新聞社として、そんなことを調べているなどということにはならんだろう。しかし、何らかの企画ということであれば、あるいは可能かもしれない。俺が紹介する形で、お前が特別企画として取材をするんだ」
「20年前の事故を再検証するといった企画を組めというのか」
「他では、まずそんなことはできないし頼めもしない。今、それが可能なのは、お前だけだ。どうだ、協力してくれないか。当時の事故を取材した元記者と現役記者の再挑戦だ。最高の企画だとは思わないか」
「何のためにだ?」
「何のため?」
「そうだ。確かに、お前の話を突き詰めて行けば、恐ろしいまでに、あの事故がどういうことだったのかを明らかにできそうにも思う。だが、今、それをして何になるんだ。あの事故が何たるかを今暴いて、どうなるというんだ。亡くなった人たちが帰ってくるわけでもない。俺は、あの時、今のお前のように、とにかく、伝えようとした。だが、真実は、決して暴いたからいいというものでもない。そっと、しておく方がいいこともあるんだ」
「何だって! お前の口からそんな言葉を聞くとは思わなかったよ。お前は、やっぱり変わってしまったよ。お前なら、すぐに同意してくれると思ったんだが、残念だ」
黒岩は、旧友に裏切られたといった面持ちで、憤りをあらわにしている。
「まあ、待てよ。俺は、お前がそういったことを調べることに決して反対などしていない。俺だって、できることなら、真相を知りたいと思うよ。だが、そういった自衛隊員や生存者と関わることが、本当にその人たちにとってプラスになるのかってことだ。被害者の家族を取材したことが、悪いことだったとは思わないにしても、俺はそっとしておいてあげれるものならそうした方が良かったと思っている。今また、同じように、その人たちを、俺たちの真相解明という興味のために利用することになりはしないか、それが気になるだけだ」
「ああ、お前が、記者を辞めた理由もそこにあったからな。しかし、お前には何かやり残したという後悔も、きっとあるだろうと思ったんだよ。もう一度、真相を追いかけるお前の姿を見たかった。あの時の、お前の姿をもう一度見たかっただけだ。確かに、お前の言うように、真相究明だなんて言っても、所詮は他人ごとの興味本位なのかもしれないよな。さっき言ったことは忘れてくれ。まあ、自分でできることを、地道にやっていくよ。また、何か分かったら教える。じゃあな」
黒岩は、まさか、福山が、こんなすごい誘いを断るなんて思いもよらなかったという顔で帰っていった。
福山は、確かに、血沸き肉踊るというほどに、興奮する企画案ではあったが、にわかに同意するわけにはいかなかった。
黒岩が言うほど、安易な興味本位でできるような企画ではない。言ってみれば、国家的謀略を暴くといった内容を、一新聞記者と一企画会社が乗り出すのは、あまりにも無謀だと言わざるを得ない。
福山は、今は、動くことにはならないと判断した。
もし、それが、本当に求められるのなら、今後にまたそういった動きが出てくるだろうと、その推移を見極めることにした。
|





邪馬台国発見
ブログ「邪馬台国は出雲に存在していた」
国産ローヤルゼリー≪山陰ローヤルゼリーセンター≫
Copyright (C) 2010 みんなで古代史を考える会 All Rights Reserved.