
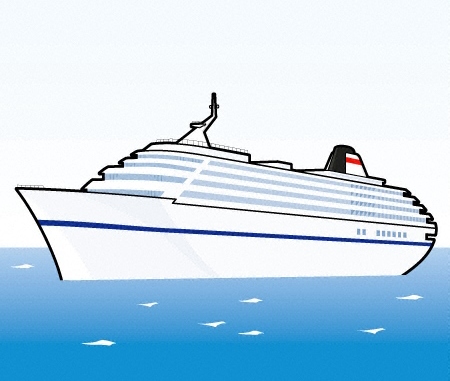

|
| 6. 秋分の日を過ぎると、ようやくこの夏の猛暑も和らいできた。 福山は、その日、松江市にあるホテルで『山陰の神話と観光』と題して講演を依頼されていた。 出雲神話は、その認識の度合いはあるとしても多くの人々が知っている。 それを生かした観光をどう推進していくかといった内容のシンポジウムで、松江市と観光協会が主催し、福山以外にも数名がパネラーとして呼ばれていた。 その基調講演ということで、全国の観光地における取り組みも紹介しながら、山陰の古代史、特に出雲神話と神社について話を進めた。 全国各地に出雲の神々が奉られていて、また奈良三輪山の近くに出雲という地名があるように、神社とともに出雲という地名も、また、今、福山が関心を持っているところだった。 子どもの頃から、出雲の神々と馴染みの深い福山にとって、常に出雲とは何か、その神々とは何を意味するのかということが心の片隅にあった。それらは、福山にとっては、神道といった宗教ではなく、この国の文化だと考えていた。 あるいは、新聞記者になったのは、そういった疑問を解き明かしたいがためだったのかもしれないし、福山にとっては、ライフワークとも言える。 シンポジウムが終わり、別室でちょっとした懇親会が持たれた。 福山が、その参加者と一通り挨拶を交わしていると、その中に、地元の山陰日報社の佐田記者が来ているのが分かった。 そして、佐田記者も、福山を見ると軽く会釈をし、福山に近づいてきた。 「福山さん、お久しぶりです」 「やあ。元気だった」 「相変わらず、ご活躍ですね。福山さんからコメントをいただきたいのですが、みなさんとお話が済まれて、お時間が取れるようになったらお願いします」 「ああ、いいよ」 その懇親会もお開きとなり、福山は、時折顔を出す居酒屋『中井亭』の暖簾をくぐった。 「いらっしゃい、これはお久しぶり」 いつものように威勢の良い大将がカウンター越しに立っていた。 「今年は本当にいつまでも暑いね」 「こうも暑いと、参ってしまうよ。そうだ、今日は、古代史好きが来ているよ。以前ここで一緒になったあの3人だ。さっきから、また話が盛り上がっているようだよ」 「そう。じゃあ、あの『東川のおじい』も居るんだ」 東川は、以前、古代史にかかわる書籍を自費出版したほどで、相当歴史には興味を持っている。興味といった域は超えているのかもしれない。 「何やら、本を見たり資料も広げて、研究熱心な人たちだ。声をかけてみるかい」 「そうだね。ちょっとご挨拶くらいはしておこうか」 福山が、その部屋を覗くと、元気の良さそうな老人と30代の男性が和やかに話をしていた。 「お久しぶりです。みなさん、楽しそうにやってますね」 「おお、これは、福山さん。今日も、このお二人からいろいろ面白いお話をお聞きしているんだよ」 東川は、ビールのジョッキを片手に上機嫌だった。 「いえいえ、こちらの方が聞き役になっています」 東川の妻はもう亡くなったが、生前介護施設に入っていて、二人は、そこの事務職として勤務している。一人は、岡田といって元埋蔵文化財センターに勤めていた。もう一人は、山中といって本当は歴史の教師になりたかったという、そんな経歴を持った歴史好きが時々集まっている 妻を亡くして淋しい東川にとっては、こうやって古代史の話ができる時が、一番の楽しみになっているらしい。 「このお二人には、生前妻が大変お世話になった。その上、こんな年寄りの古代史の話にも付き合ってくれる。本当に感謝しているよ」 東川は、鼻をグスグス言わせながら話している。 「こちらこそ、お話が聞けてうれしいですよ」 岡田が、涙もろくなっている東川を慰めている。さすがは、介護施設に勤めているだけあって、老人の相手が上手だ。 「さて、どこまで話したかな。さあ、福山さんもそんなところに立っていないで、ここに座んなさい」 「ええっ、そ、そうですか。じゃあ、ちょっとだけ」 福山は、断るのもどうかと思い、空いている東川の隣に座った。 「そうだ。わしは、若い頃戦争に行っていたという話をしていたんだ。その頃は、学校でこの国の歴史が、徹底して教え込まれた。それも、あり得もしない架空の歴史認識をだ。しかし、その頃は、そんなことなど解りゃしないから、真剣に、この国は、いざという時には神風が吹いて、絶対に負けることなどないと固く信じておった。わしは、北京のさらに北の前線に送られてな。冬になると何もかもが凍ってしまうんだ。それで、わしは、体を壊して本国送りとなったというお粗末な話だ。その時は、お国の為に役に立てないと情けなかったもんだ。家や近所にも顔向けができないと、帰る船や汽車の中で泣いていたよ。戦死した方が、まだましだと真剣思っていた」 「そうですか。それは、大変でしたね」 福山が、東川の苦労を慰めようとした。 「ところが、その病気が幸いしたというか、それ以後は日に日に戦況が悪化し、わしより後に帰国する船は、次から次と潜水艦に沈められてしまって、本当に命びろいをした」 「それは、本当に良かったですね」 「本当に。でなければ、どうして自分が戦争になんか行くことになったのかも知らずに死んでいるところだった。そうだ、福山さん。さっきも話をしたんだが、この列島には悪魔が住み着いているんだよ」 「悪魔が?」 福山は、東川が急に何を言い出すのだろうと思った。 「そう。悪魔だよ。この国の奥深く潜んでいて、多くの人々を、洗脳してしまうんだ。その悪魔に一度洗脳されたら、もう終わりだ。逆らうことなどできず、その悪魔の思うがままに操られてしまう。そして、銃剣を振り回して、大陸へ侵略していくんだ。この列島は、殆ど、鬼が島だよ」 「東川さん、そんな悪魔だなんて根拠のないことを言っちゃだめですよ」 「福山さんも気をつけた方がいいよ。いろいろ研究熱心な人ほど、その悪魔に魅入られてしまうんだ。そして、誰も洗脳されているなんて思いもしないうちに、逃れられない悪魔の領域に引きづり込まれてしまう」 「なんか、ちょっと怖い話になってきましたね」 「わが国の歴史は、そういうことなんだよ。悪魔の呪文のようなものだよ。でも、誰も悪魔がいるなんて思いもしない」 「当たり前ですよ。今の時代に、悪魔だなんて、まるで中世の頃の話じゃないですか」 福山は、東川が、かなり酔っているように思えた。 「ところで東川さん、今日は、この国の歴史に大きな影響を与えた渡来民族のお話ということでしたが」 静かに飲んでいた山中が、東川に話を元の方向へ戻すように促した。 「おお、そうだった」 「渡来民族ですか。それは、僕も聞きたいですね」 福山も、ちょっと興味をそそられた。 東川は、そばに置いていた資料を手にした。 「ここにも書いているように、紀元前4世紀頃、アレキサンダー大王が、インダス川のあたりまで、東征するんだ。そうなると、そこに住んでいた人々は、殺されたり奴隷にされてしまうから逃げるしかない。しかし、東へ行ってもそこはタクラマカン砂漠など人があまり住めるような場所ではない。したがって、さらに東へ東へとやって来ると東アジアにまで到達することになる」 「ということは、中央アジアの民族が東アジアにやって来たということですか」 岡田が、資料を見ながら聞いた。 「そうだよ。中央アジアのあたりには、トルコ系の民族が住んでいて、今でもその地は、トルコ民族の地という意味で、トルキスタンと呼ばれている。その流れてきたトルコ系の民族を中国王朝は、『胡』と呼んだ。彼らは、この列島にもやってきて多くの文化を伝えている。きゅうり(胡瓜)、クルミ(胡桃)、アグラ(胡坐)などなど数え切れないほどあるよ」 「そうですか。でも、そんな民族のことなど、あまり聞いたことないですよねえ」 山中も、資料を見つめながら東川に聞いていた。 「中央アジアからやってきた胡の勢力には、大きくは3つ、『月氏(げっし)、匈奴(きょうど)、東胡(とうこ)』とあった。彼らは、同系列の民族ではあるが、お互いが牽制しあってもいた。東胡は、一番東、いわゆる満州と言われたあたりに位置し、モンゴル地域に匈奴が、そして、その西に月氏がそれぞれ、住み分けていたんだ。彼らの一部は、この列島にもたどり着き、その歴史は出雲神話にも残されているよ」 福山は、先ほど講演をしてきた神話の話が出て、ちょっと驚いた。あの出雲神話のどこに渡来民族の歴史が描かれていたのだろうと不思議に思った。 「出雲神話にですか」 「そうだよ。それらの民族のひとつ匈奴には、単于(ぜんう)、すなわち皇帝を意味する種族の長がいた。紀元前2世紀頃になり、頭慢(とうばん)単于の時代のことだった。頭慢は、当初、息子の冒頓(ぼくとつ)を後継者として考えていたが、次第に、後妻の息子を後継者にしようと考えるようになってしまった。そうなると、どうしても、冒頓のことが邪魔になってくる。そこで父である頭慢はどうしたと思う?』 そう言って、東川は、岡田の方を見た。 「さあ、どうしたんでしょう」 「先ほども言ったように、その3国はお互いが牽制しあっていたから、頭慢は、息子の冒頓を人質として隣国の月氏に送るんだよ。そうすると、月氏は、息子を人質にしているから、まさか匈奴が攻め入るなどとは思いもよらない。ところが、頭慢は、ほどなくして月氏に攻め入るんだよ」 「ええっ、そんなことをしたら息子が殺されてしまいますよ。あっ。ああ、そういうことですか、頭慢は冒頓の抹殺を仕組んだのですね」 「さすが、福山さん。よくお分かりで、そうなると、冒頓は危険にさらされてしまう。福山さんのように察しの早い冒頓は、馬を奪い、戦乱の中を掻い潜り、頭慢の元に帰りつくんだ。父頭慢は、よくぞ帰って来たと迎えるが、冒頓は当然いつか自分が殺される運命にあることを悟る。そして、冒頓は、大きな策略を考えたんだよ。どんな策略を考えたと思う?」 東川は、山中の顔を見ながら聞いた。 「どうなんでしょうねえ」 山中は、知る由もなく首をかしげた。 「まず、冒頓は、配下の者を連れて野に出て、今後自分が矢を放ったらみな一斉に同じ方向に矢を放てと命令した。そして、獣に向けて矢を放ち、その時に矢を放たない者は切り捨ててしまったんだよ。次には、自分の愛馬に向けて矢を放ち、同じく矢を射らない者は切り殺してしまった。更に、自分の愛妾を射て、また矢を射らない者を切り捨ててしまうんだ。さて、冒頓は、どうして、こんなことをしたと思う?」 次は、福山の顔を見た。 「そうですねえ。絶対服従を徹底したということでしょうか」 「ほう、福山さんには、首領の才能がおありなのかもしれないね。自分の配下には、絶対の信頼を置ける者だけを残し、ある時、前を通る父頭慢に向けて冒頓は矢を射るんだ。すると、みないっせいに矢を放ち、頭慢を殺害し、さらに母や兄弟もすべて抹殺し、冒頓は、そこで単于に即位し、絶対的な支配力を確立したんだ。それ以後、匈奴は、モンゴル地域を中心に大きな勢力を築くことになったというお話だ」 「んん~、なんかちょっと悲しいお話でもありますね」 「それを知った隣国の東胡は、それをチャンスと見て匈奴にちょっかいを出すんだが・・・」 そこまで話すと、東川はビールを一口飲み、静かにうつむいてしまった。 「どうしました? 東川さん?」 福山は、東川の肩をたたいた。 「あ~あ、寝てしまいましたか。最後は、いつもこうですから。じゃあ、今日は自分が送っていきます」 岡田が、立ち上がり、カウンターでタクシーを頼んでいた。 「最近は、歴史の話というより、講談といった調子になっています」 山中が、残っていたビールを飲み干していた。 「よくお相手されますね」 「まあ、歴史の話をしながら飲むのは嫌いじゃないですからね」 その日は、次の店に行くこともなくそれぞれ帰ることになった。 福山は、いろいろ聞きはしたが、果たしてそれをどう理解したものかと考えながら実家へむけてタクシーに乗った。 出雲神話に渡来民族の話が描かれているというところをもう少し詳しく知りたかったが、次の機会を待つしかなかった。
|


邪馬台国発見
ブログ「邪馬台国は出雲に存在していた」
国産ローヤルゼリー≪山陰ローヤルゼリーセンター≫
Copyright (C) 2010 みんなで古代史を考える会 All Rights Reserved.