
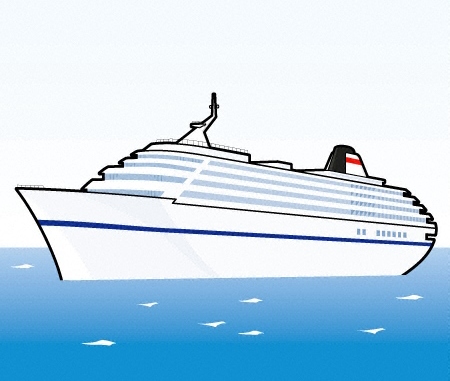

|
| 2. 二人が現地に着くと、続々と人が押しかけていた。 報道関係者や横浜大洋汽船の社員、自治体関係者、さらに警察、自衛隊、海上保安庁と見られる人々でごった返していた。 2階大会議室に会見場が設けられていた。 「俺はここで情報を集めるから、お前は乗員乗客のリストを手に入れてくれ」 「分かった」 黒岩は、その階の奥にある対策本部へ向かった。 福山は、まず、近くにいる横浜大洋汽船の社員に声をかけた。 「すみません。T新聞です。乗員乗客の安否はどうなんですか」 「私にも分かりません。間もなく記者会見が始まりますので、それを聞いてください」 まだ、詳しい情報が入っていないのかもしれない。 福山は、以前取材したことのある県警の公安部長の姿が見えたので、それとなく近づいた。 「大変なことになりましたね。この沈没は、どういうことなんでしょうか」 「私にもまだ分からん。現在調査中だよ」 「そうですか」 福山が、また他を当ろうとしていると、本社の運行担当部長による会見が始まった。 「このたびは、大変な事になりまして、誠に申し訳ありません。私どもも、現在必死で情報を収集しているところでありますが、沈没したということ以外には、まだ十分に把握ができていません。今しばらくお待ちください。以上です」 簡単な記者会見だった。とりあえずのところだろうが、記者からの数々出されていた質問にも殆ど答えられていなかった。ただ、ただ平身低頭謝罪の言葉を述べていた。 「おい、福山。乗船名簿が手に入った。それと、奥で気になることを耳にした」 「なんだ」 「米軍が救助に向かっていると言っていた」 「米軍が?」 「ああ、どうも近くに米軍の戦艦か潜水艦がいるようなことを言っていた。しかし、確認を取ろうとしたらはぐらかされたから、何とも言えないけどな」 「米軍か。だが、連絡は自衛隊から入ったと先ほどのニュースでは言っていたが、どういうことなんだろう」 「米軍と自衛隊が、その付近にいたということなのか?」 「よく分からんが、とりあえず、デスクには伝えておけ」 「よし」 黒岩は、支社に連絡を入れ、福山は、引き続き周辺で情報収集に走った。 しばらくして、黒岩が戻ってきた。 「おい。テレビの報道では、まだ事故現場が分かっていないと言っているそうだ」 「現場が特定できていないだと? じゃあ、さっきの救助に向かったというのは、どういうことだ」 「さあ、分からん」 「よし、自衛隊と米軍の基地へ行こう」 「ここはいいのか?」 「ここで発表されることぐらい、支社でもつかめる。行くぞ黒岩」 黒岩は、持ち場を離れるのに少々不安だったが、福山に続いた。 二人が、支社に戻ると、本社からの応援も入り、今までにない慌しさだった。 「こらあ、黒岩、30分ごとに連絡を入れろと言っていたのに、どうして連絡を入れないんだ」 高山デスクの怒りの声が轟いた。 「あ、別の所に取材を」 「別って、どこだ?」 「自衛隊と米軍基地へ」 「何だと! 誰がそんなところへ行けと言った。お前らは大洋汽船で取材しろと言っただろう」 「すみません。俺がそうすると言ったから」 「福山が? お前にどうしてそんな判断ができるんだ」 「もう、乗船名簿は手に入ったし、あれ以上居てもそんなに情報は入りそうに無かったもので。それより、デスク、どうもこの沈没には米軍や自衛隊が絡んでいるようなんです」 「米軍や自衛隊が? その根拠は?」 「黒岩が、事故現場の近くに米軍が居たようなことを耳にしたんです。それに第1報は自衛隊だし、そんな気がしてならないんです」 「『気がして』だと? 誰もお前の感想など聞いていない。で、その米軍や自衛隊では何か裏が取れたのか?」 「それは、何も」 「それなら、どうにもならんだろう。とにかく勝手に動くな。乗船名簿はすぐに本社編集局に回せ。以上だ」 テレビの報道は、現在、オーシャン・ドリーム号の事故現場を特定するため自衛隊と海上保安庁の捜索機が夜を徹して捜索中だというニュースを繰り返し報道していた。 「どうする福山」 「俺らには、これ以上どうすることもできんよ。その捜索とやらのその後を待つとしよう」 「そうだな」 「どちらにしても、今日は帰れんな」 福山は、仮眠室に向かった。 黒岩は、テレビ画面を見ながら、先ほどの米軍が救助に向かったというのは、何だったんだろうと思い返していた。 次の日の朝、オーシャン・ドリーム号の沈没現場を報道していた。 その映像から、一帯には、油や船の一部と見られる破片や、乗客の持物などが波に揺られているのが分かった。 浮かんでいる被害者の姿は見えなかったが、あるいは、すでに引き上げられていたのかもしれない。 海上保安庁や自衛隊の船が、それらの残骸を回収していた。 「黒岩、生存者は?」 「ああ、どうもいないみたいなことを言っている」 「一人もか?」 「まあ、まだ周辺を捜索しているようだから、どうなるか分からないがな」 「原因については何か言っているか?」 「それも、何も」 その船名のごとく夢にあふれた豪華客船の処女航海が、出航したその夜、突然恐ろしいまでの悲劇と化してしまった。 乗員乗客合わせて352名が、船もろとも太平洋に沈んでしまったのか。 そうなると、戦後では、1954年に青函連絡船「洞爺丸」が台風の暴風により転覆沈没し、乗員乗客1155名が犠牲になって以来の大惨事だ。 そして、昼過ぎのことだった。 「先ほど、海上保安庁に入った連絡によりますと、生存者が1名確認された模様です。繰り返します・・・」 そのニュースに編集部は沸き立った。 「ようし。『奇跡の生存者発見』だ。福山、すぐに、大洋汽船へ行って、そこにいる大下と交代だ。また持ち場を離れるな。いいな」 「はい」 福山は、すぐに支社を出た。 亡くなった人たちは本当に無念だったろうが、たとえ一人でも生還できたことはせめてもの朗報だった。 大洋汽船には、その被害者となった人々の家族が詰め掛けていた。 生存者の確認がそこでも伝えられていて、もう居ないのか、せめて自分の身内がと祈るような面持ちだった。 とても、取材をする気になれなかったが、福山はその人たちのコメントを集めることにした。 福山の取材した被害者の家族の声には、多くの人々が心を打たれた。
|


邪馬台国発見
ブログ「邪馬台国は出雲に存在していた」
国産ローヤルゼリー≪山陰ローヤルゼリーセンター≫
Copyright (C) 2010 みんなで古代史を考える会 All Rights Reserved.