
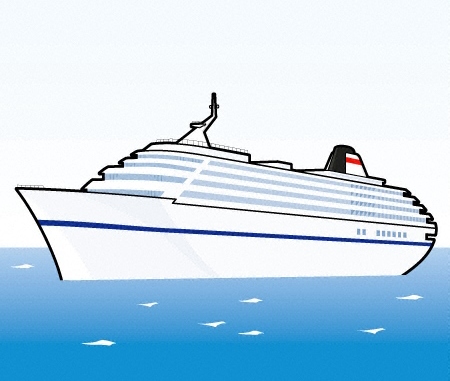

|
| 9. 十月にもなると、すっかり秋らしくなり、日差しもおだやかになった。 黒岩は、公園を散歩する人の姿を眺めながら、指定された午後1時に代々木公園にやって来て、池の周辺に設置されているベンチに腰掛けていた。 すると、帽子を深めにかぶった男性が、コンビニで買ってきたと思われるビニール袋を片手にしながらこちらに歩いてくる。 そして、黒岩の隣に腰をかけ、その袋からパンを取り出して食べ始めた。 その男性は、横を向いているので、顔は良く見えない。 「おだやかないい天気ですねえ」 斉藤の声だ。 「本当に心地よいですね」 黒岩も静かに答えた。 これでお互いの確認ができた。 だが、斉藤は横を向いたままだ。 「いいか、俺の方は見るな。俺がここでパンを食い終わるまでの間に、聞きたいことがあれば俺の分かる範囲で答えてやる」 斉藤が、小声で言った。 「では、まず、オーシャン・ドリーム号の事故の日、日米の共同訓練があの付近で行われていたようだが、その訓練の内容はなんだ?」 「当時、アメリカは、追尾型ミサイル、トマホークの開発に力を入れており、日本もそれに全面協力をしていた。対空型は、かなり進んでいたが、魚雷型はまだ開発途上にあった。それが、ほぼ完成に近づいたので、その試行実験をしていたと聞いている」 「その実験と事故に関連があると見ているんだが、実際はどうなんだ」 「それは、一切他言無用のことなので、俺のところにも届いてないが、おそらく、そのダミー、おとりの船がオーシャン・ドリーム号に接触したのだろう。そうなると、それを追尾してきた試験用ミサイルは、オーシャン・ドリーム号が標的だと認識してしまったと思われる。おそらく、スクリューをターゲットとしてセットしてあるから、船尾を破壊したのだろう」 「それによって、沈んでしまったのか」 「試験用だから、そこまでの破壊力はない。小さな船を吹っ飛ばすほどの威力はあるが、大型客船をただちに沈めるだけの威力ではない」 「じゃあ、どうしてドリーム号は、沈んだ。それも、緊急事態を知らせてから、かなり短時間にだ」 「それは、テープを聴けば分かる。ヒントは、当時、中性子爆弾の魚雷も開発中だったということもある」 「何だって! 核兵器が使われたというのか」 「しっ、声が高い。いいか、俺はそこまでは言っていない。そういう背景があったということだ」 身の毛も、よだつような話である。 「次に、どうして、すぐに、救助に行かなかった。米軍も近くにいたはずだ」 「だから、直ぐに近づける訳がないだろう、そんな危険な区域に」 「そうか、なるほど。だから、帰還させたのか。人命救助なんてどうでも良かったのか」 黒岩は、怒りがこみ上げてきて、斉藤に言ってもどうしようもないのは分かっていたが、止めることができなかった。 「お前なあ、自衛隊は、救助隊じゃないんだ。人を殺す訓練はするが、助ける訓練などしない。まして、当時は、国際的にも国内でも、核戦略については極めて微妙な情勢にあった。そんな中で、そんな訓練をしていたことがばれるだけでも大変なことだ。上層部は、あらゆる痕跡を消して、政治問題にならないことだけを最優先に考えていた」 「人命救助よりも、証拠隠滅を図っていたというのか」 「おそらく、明け方までに、潜水艦で重要な証拠は回収してしまったのだろう。だが、すべては、回収しきれなかった。調査資料の中にも写っていたオレンジ色のついたものは、ダミー船のものだ。そういった事情だったので、事故現場の確認を遅らせたということだ」 「だが、たとえ明け方になったとしても、生存者は他にもいなかったのか」 「あらゆる痕跡を消そうとしたと言っただろう」 「何だと。生存者も消してしまったというのか」 声は小さいが、口調は激しさを増した。 「そんなことは、俺には分からない。ただ、あらゆる都合の悪い痕跡は、消し去ろうとした。あるいは、特殊部隊が出動したのかもしれない」 「特殊部隊だと?」 「いくらなんでも、自衛隊員が自国民の殺戮はできんだろう。だから、外人の傭兵部隊があるという話を聞いたことがある。お金で雇われた外人なら、何でもするだろう。あくまで秘密の部隊だから、自衛隊員もほとんど知らない。隠密の国営テロ組織だよ。電子銃といった武器も装備しているとも聞いた。それが使用されても痕跡を残さないから、見た目には急性心不全かといったことにしかならない。ただ、俺も確認した訳ではないから、憶測の域を出ないがな」 黒岩は、そんなことがあり得るのかと、言葉も出なかった。 「夜陰に乗じて、沈められる物は沈め、沈められない物は回収したんだよ。その現場が『特定』されるまでの間にな。そして、夜が明けたら、次は、『救助』を命じられた部隊が必死に捜索する姿をテレビやマスコミに報道させるという手順だ。300人以上の罪なき人々を殺戮したテロ集団を、まるで瀕死の被害者を助ける『救助隊・正義のヒーロー』かのごとくに日本全国の国民には思わせた。だから、あの生存者は、その特殊部隊に発見されなかったのが幸いしたのだろう」 聞けば聞くほど、怒りがこみ上げてくる。これでは、殺されたということではないか。 「その生存者は、今どこにいる」 「命は助かったが後遺症による下半身不随のため、国立の療養所にいると聞いている。まあ、余計なことをしゃべらないように、都合よく口封じのために監禁をしているということなのかもしれない」 すでに、斉藤は、パンを食べ終わっていた。 「では、最後に、どうして話をしてくれる気になった」 「自衛隊員とて、人の子だ。親もいれば家族もある。この国を守るという使命を持って入隊をしてくる者もいれば、就職難で、やむなく来る者もいる。それは、それぞれだ。だから、自殺するなんてあり得ん話だ。ほとんどは自殺に追い込まれたか、自殺に見せかけられたかだ。俺と同郷の若いやつがいてな。そいつは、親に仕送りをしていたんだ。同郷のよしみで、時々、話をすることがあった。また、故郷に帰ったら会いましょうなんて言うような、いいやつだったよ。そいつが、昨年、拳銃自殺した。あいつが、自殺なんかするわけがない」 斉藤の言葉には、静かながら怒りがこもってきたように思えた。 「お前ら、自衛隊なんて名称だから、この国を守っている、自分らを守ってくれているなんて思っているだろうが、上層部は、そんなことなんか、ちっとも考えてなんかいるもんか。災害出動や海外での救援活動なんてものは、本性を偽るための見せ掛けに過ぎん。広報にいる俺がそれを一番よく知っている。さっきも言ったが、自衛隊は、救助部隊なんかじゃない。最近は、特にそうだ。人を殺す訓練が徹底されている。そして、自分の頭で考えさせないようにしている。ただ命令に従うだけの殺人集団にされつつある。殺人マシーンの製造機関だ」 「なんて恐ろしいことだ」 「そして、上司や命令に逆らったら死の制裁だ。俺も自衛隊員のはしくれだが、こんな自衛隊なんかじゃ好きになれんし、誇りにも思えん。だが、そんな自衛隊を必要としている奴らがいるんだろうな。さあ、そろそろ帰るぞ。その袋の中に渡す物が入っている。俺は袋を忘れていくから、お前は、ゴミを捨てる振りをして、中の物を持って帰れ。それをどうするかはお前が考えろ。じゃあな」 斉藤は、立ち上がり、そのまま来た方向へ帰っていった。 黒岩は、ベンチに残されたビニール袋を持ち、歩きながら中を探ると、カセットテープが入っていた。そして、それをそっと抜き取り、ビニール袋は、ゴミ箱へ捨てた。 そのテープには、いったい何が録音されているのか。 黒岩は、少々、周りを気にしながら家路についた。 そして、そのテープを聴くと、あまりに恐ろしく驚くべき内容で、再度話をしようと、翌日、福山に電話をかけた。
|


邪馬台国発見
ブログ「邪馬台国は出雲に存在していた」
国産ローヤルゼリー≪山陰ローヤルゼリーセンター≫
Copyright (C) 2010 みんなで古代史を考える会 All Rights Reserved.